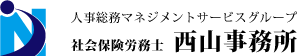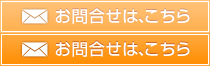中小企業の業績悪化のパターンと企業再生④ - まず着手すべきはコストの削減
2013/02/11|ビジネスコラム
まず着手すべきはコストの削減
企業経営の目的を簡単に言ってしまうと、利益をあげることです。
利益をあげるためには、①収入である売上高をできるだけ上げること、②支出であるコスト(経費)をできるだけおさえること、が必要です。
経営者の方に、赤字の要因をお尋ねすると、よく以下のようなお返事をいただきます。
「販売不振が原因 → だから、営業強化や販売促進に力を入れたい」
「燃料代(材料代)が上がったから → どうしようもない。売上高を上げるしかない」 など
これは主に、上記①の「収入である売上高をできるだけ上げること」に主眼をおいて、お話をされているのだと思います。
このようなお考えも、決して間違ってはいません。
しかし、過去の決算書(貸借対照表、損益計算書)をよく調べてみると、売上高とコストのバランスが明らかに悪化していることが多いのです。
本稿で何度も申し上げています”コスト構造が破綻している”ケースです。
例えば、粗利益率〔(売上高-原価)/売上高〕が低下しているケースや、売上高対労務費比率が悪化しているケースなど。
このようなケースでは、いくら頑張って①の「収入である売上高をできるだけ上げること」に努力しても、赤字からの脱却には効果が薄いのです。
逆に売れば売るほど、赤字になることさえあるのです。
また、売上高を上げるということは、相手(顧客)あっての話しになりますので、確実性が低いのです。
(一方、コストの削減は、内部のことが多いので努力次第で効果がすぐに現れます。)
さらに言えることは、中小企業の経営者は大変忙しく、また使える経営資源(人、モノ、金)も限られていることから、あれもこれもできない、やれることは限られているという制約があることです。
したがって、中小企業が赤字体質(コスト構造が破綻しているケース)から脱却を図ろうとするのであれば、②の「支出であるコスト(経費)をできるだけおさえること」に、まずは全力を傾けることが重要と私は考えます。
「入るを量り、出を制する」という言葉(意味:収入を勘案してそれに見合った支出を心がける。)がありますが、まさにこれが重要な考え方だと思います。
すなわちコスト構造の改革です。勿論、簡単にできることではないのですが。